
病院に入通院していたにもかかわらず,自身・親族の病状が悪化した,親族が死亡したなどの場合はやるせないですよね。
特に,何らかの特異的事象が生じた場合には,なぜ自分が,なぜ愛する家族がこんな目にあうのかという悲しみから,その矛先が医師・医療機関に向かうこともあります。
この様な場合に,医療ミスがあったと主張して患者側から医療機関の責任追及を求めることがなされるのがいわゆる医療過誤事件です。
【目次(タップ可)】
医療過誤訴訟の困難性
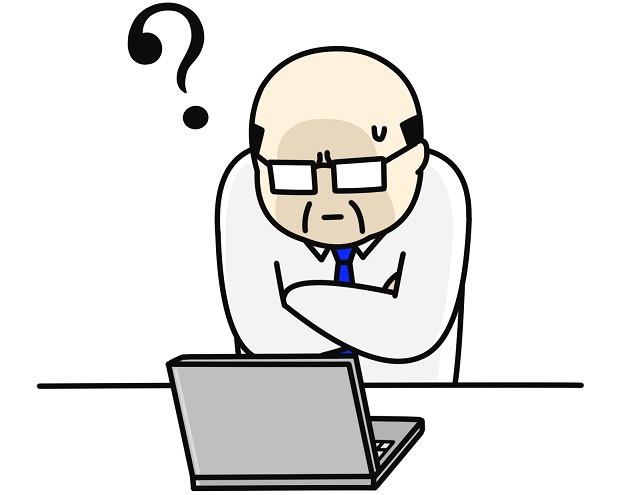
医療過誤事件の特色
医療過誤事件は,実際始めてみると痛感されると思いますが,医療過誤事件は,とても難しい事件類型です。
それは患者側家族にとってはもちろんですが,患者側弁護士にとっても同様です。経験の少ない若手弁護士では,大した知識もなく簡単に着手してしまう人もいるらしいですが,信じられません。
特に,医療過誤訴訟にまで発展してしまうと厄介です。
実際,医療過誤訴訟における原告勝訴率は,以下のとおり20%を下回る数値となっています,通常訴訟事件の原告勝訴率が80%を超えていることと比べると,驚くべき低い数値です(裁判所ホームページ参照)。
①平成30年:18.5%(通常訴訟85.5%)
②平成29年:20.5%(通常訴訟84.9%)
③平成28年:17.6%(通常訴訟80.0%)
④平成27年:20.6%(通常訴訟83.3%)
⑤平成26年:20.4%(通常訴訟83.7%)
弁護士の印象としては,医療過誤事件は,訴訟になるとなかなか勝てない事件であるという印象です。
医療過誤事件の原告勝訴率が低い理由
では,なぜ医療過誤訴訟の勝訴率はこんなに低いのでしょうか。
色々理由がありますが,主な理由は以下のものです。
①医療過誤が明らかな場合には示談で終わことが多い
医療過誤訴訟の場合,訴訟における医療機関側の実質的遂行者は保険会社(及びその代理人弁護士)です。
保険会社は,金銭支払能力に問題がない上,不利益な裁判例が出されることを嫌いますので,医療機関側に過失が明らかとされる事案の場合には,早々に示談金を支払って終わらせてしまいます。また,請求額が少額である場合も,訴訟提起に至ることなく終了することが多いといえます。
そのため,患者側勝ち筋の事件は,そもそも訴訟に至らずに終わることが多いのです。
②担当弁護の力量が不足している場合が多い
医療過誤事件を扱う場合には,患者側(具体的には,患者側弁護士)において,患者の被った損害,医療機関側の具体的過失行為,両者の因果関係について,医学的に主張・立証する必要があります。
医師・医療機関側において適切な治療をしていたにもかかわらず(過失がないにもかかわらず),病態が急変して患者が死亡することはあり得ます。
そこで,医療過誤といえるためには,段階的・複合的な医療行為の中から,損害に直結する行為を抽出しなければなりません。
これは,医療の素人である法律家には難題です。
何をしていれば損害発生は避けられたのか(結果回避可能性),その当時の医療水準に従ってまたその行為を強いることは過酷ではないのか(結果予見義務)の判断が出来なければ,本来医療過誤とはいえない事件を,患者又はその家族の感情に引きずれれて事件化してしまう。
以上の過失行為を判断するためには,医療記録の読解も必要です。
医療記録は,一般に,診療録(医師法24条,同規則23条),看護記録,各種記録,画像,診療報酬明細書等で構成されています。
いずれにしても,その全ては医療機関側が有しています。保存期間については,診療録は5年間(医師法24条2項),その他は2年間(医療法21条1項14号,同施行規則20条11号)とされています。
そのため,医療過誤の有無を判断するためには,まずこれらの証拠を集めることから始めなければなりません(読解の前提として,収集も問題となります。)。
なお,収集方法としては,医療機関に対して任意に開示を依頼する場合や,裁判所を通じた検証手続きである証拠保全(民事訴訟法234条~)の方法による場合などがあります。
この点,かつては診療録改ざん防止の観点から,医療記録の収集は証拠保全によることが当然のように言われていましたが,近年では電子カルテの浸透により,改ざんが困難となってきていますので,最近は,証拠保全によることなく任意開示により医療関係資料の取り付けを行うことが一般的になってきています。
③協力医の確保の困難性
医療の素人である弁護士が,前記のような医療分野の問題を扱うこととなる以上,カルテの解読,画像の読影,医療水準の判断等の全てにおいて専門家のアドバイスは必須となってきます。
そこで,通常は,協力医を探して協力してもらうことが必要となってきますが,これもまた厄介です。
まず,候補者を探すだけでも相当の労力を要します。
また,協力をしてもらえる医師が見つかっても,匿名のアドバイス程度にとどまることが多く,意見書の作成や法廷に出廷して意見を述べてくれる程度の協力を仰ぐには極めて高いハードルがあります(医師にとっても,仲間といえる他の医師の糾弾に協力してくれる可能性は高くありません。)。
④境界事例の場合も多い
さらには,医療行為自体が境界事例の場合には,さらなる困難さがあります。
何らかの救済が必要とも思える事案であるものの,立証責任という訴訟上の問題で原告側敗訴という可能性があるからです(医師の技量不足を問題とする場合等)。
医療過誤事件を弁護士に委任する場合の流れ

相談
一般事件とは異なり,医療過誤事件では相談段階で弁護士が見立てを立てることができません。医療記録の収集・分析がなければ前提事実すらわかり得ないからです。
そこで,医療過誤事件では,相談後,事件受任の前に,資料収集及び調査という手順を経ていくこととなります。
調査
①医療記録の収集
そこで,まずは,医療過誤事件であるとの相談があった場合には,医療記録収集を行うことから始めます。
この点,医療機関には,カルテは5年間(医師法24条2項),その他の記録は2年間(医療法21条1項14号,同施行規則20条11号)の保管義務がありますので,これらの記録を,任意開示,証拠保全,裁判所による鑑定等の手続きによってこれをとりよせる必要があります。
②医療記録の分析
前記で取り寄せた医療記録について,その分析を行い,文献調査や協力医師の協力を得て,損害,過失,因果関係の有無を立証できるか検討していくこととなります。
なお,この時点で,法律問題とは考えられない場合,医療機関側の過失行為が観念できない場合,相談者と信頼関係が築けない場合,費用対効果が合わない場合などは,委任に至ることなく事件終了となります。
事件委任:示談交渉・法的手続き
以上の調査を経て,弁護士において,一応,医療水準を踏まえた上で医療機関側に損害発生に直結する過失が認定できると判断した場合には,ようやく事件受任に至ることとなり,長い戦いに入って行くこととなります。
以上が,医療過誤事件のあらすじと,その困難性についての概略でした。参考にしてください。