
普段はあまり気にも留めていないかもしれませんが,道路上を走行しているバイクのほとんどは,昼間であってもヘッドライトを点灯させています。
なぜでしょうか。
道路上を走行する二輪車(バイク)は,いついかなるときも前照灯(ヘッドライト)を点灯させていなければならないのでしょうか。
以下,知っているようで,実はあまり知られていない二輪車の前照灯灯火義務について説明します。
【目次(タップ可)】
道路交通法の前照灯灯火義務とは
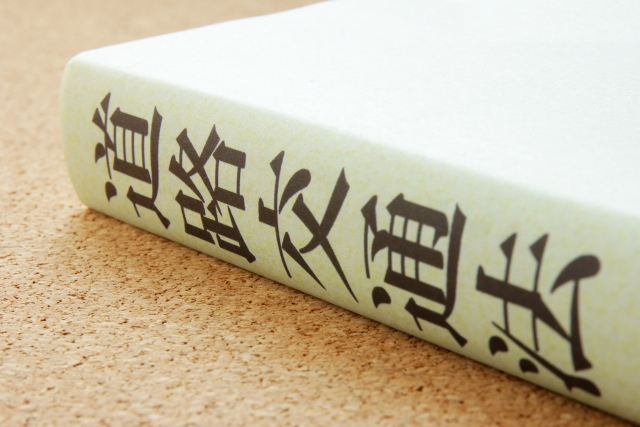
道路交通法では,夜間に道路にある車両は前照灯(及び車幅等・尾灯・その他灯火)をつけなければならないとされています(道路交通法52条1項)。
ここでいう「車両」とは,自動車のみならず,二輪車の法区分に関係なく二輪車全般が含まれます。
また,「夜間」とは,日没時から日出時までの時間をいいます。天然の暦によって判断されますので,夜間の範囲は日本全国一律ではなく,地方や四季によって異なることになります。
さらに,「道路にある」とは,道路通行時はもちろん,駐停車も含まれます。
以上より,道路交通法上は,二輪車は,夜間に道路を走行する際には前照灯を点灯させなければならない義務を負うこととなる一方で,昼間に道路を走行する際には前照灯化義務を負わないこととなります。
道路運送車両法の保安基準
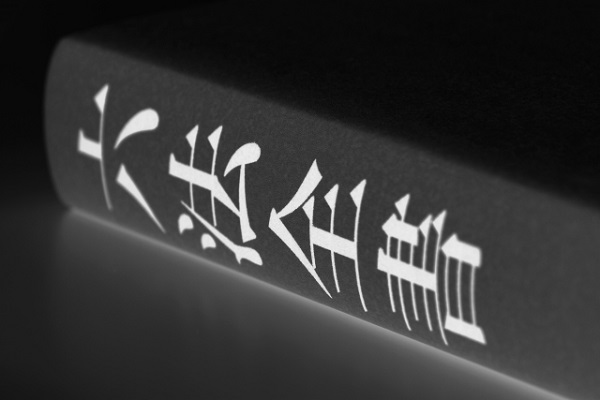
もっとも,安全面から見ると,二輪車は,その運転手自体の視界の確保の観点のみならず,他の車両等からの視認性の確保の観点から日中であっても前照灯を点灯させていた方がいいことに異論はありません。
そこで,1998年(平成10年)4月1日に施行された国土交通省「道路運送車両法の保安基準」32条により,二輪車について,原動機が作動している場合には常に走行用あるいはすれ違い用の前照灯のいずれかが点灯している構造としなければならないとの技術基準が定められました。
この技術基準により1998年4月1日以降に販売される全ての二輪車については,エンジン点火と同時に前照灯が点灯し,かつスイッチ等で消灯することができない構造としなければならなくなりました(1998年4月1日以降に販売された二輪車については,スイッチをつけて消灯できるように改造すると車検を通らなくなりました。)。
なお,1998年3月31日以前に製造・販売された二輪車については,前照灯の常時点灯構造を有している必要はありません。
まとめ

以上のとおり,建前としては終日前照灯灯火義務を課したいものの,いまだに1998年3月31日以前に製造された前照灯を消灯できるスイッチが付いた二輪車も現役で走行しているため,終日前照灯灯火義務を課すことまではできない状況下にあると言えます。
そこで,道路交通法上は,夜間のみ前照灯灯火義務を課すこととするにとどめることとしています。
そのため,夜間に限り,前照灯を点灯させていない状態で二輪車を運転していれば,道路交通法52条違反となり,また交通事故に遭った場合には,二輪車に不利益に斟酌されます。
他方,道路交通法上,昼間に点灯義務はありません。
そこで,日中に前照灯を点灯させていない状態で二輪車を運転していたとしても,道路交通法違反はありません。
そのため,日中の前照灯不灯火が,二輪車の過失に不利益に働くことはありません。
もっとも,道路運送車両法の保安基準によって事実上の昼間の前照灯点灯が義務付けられている状況下にあり,1998年3月31日以前に製造・販売された二輪車が市中にいなくなった後は,法律上,日中に前照灯無灯火で走行車両はいなくなることになります。
その意味で,現在は,事実上の日中の前照灯灯火義務への移行時期にあると言えます。
参考にして下さい。
流石弁護士さんです。漸く納得できる記述に出会いました。思った通りです。
二輪車に乗っていて、常時点灯車ではパッシングの効果が殆ど無くなってしまうので、スイッチで消灯できるように改造しようとかんがえ、法的根拠を探していました。
結果どうするか?勿論安全に寄与する方を選択します。ありがとうございます。
1998年3月31日以前に製造・販売された二輪車に前照灯を消灯・点灯するための切り替え装置を付加するのは法律違反になるのでしょうか?ちなみに私が所有米国製オートバイの製造年式は1989年です。
29条7項に関する例外規定の読み方が複雑すぎて困っています。
https://www.mlit.go.jp/common/001056497.pdf
平成10年3月31日以前に製作された二輪自動車及び側車付
二輪自動車(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年
10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受け
た型式認定自動車を除く。)